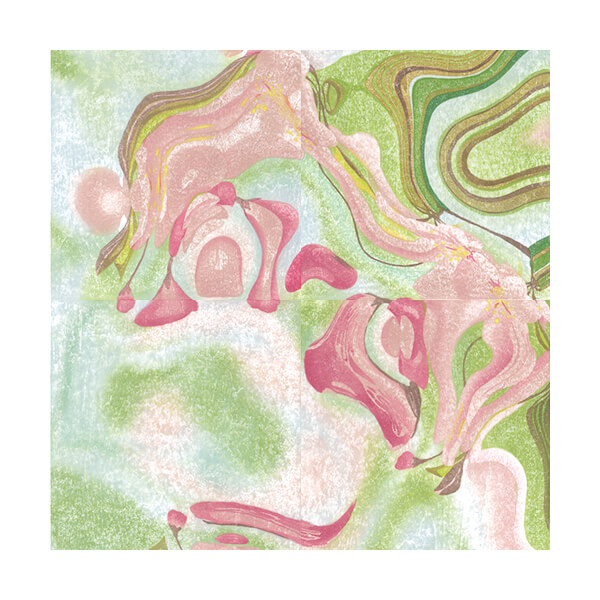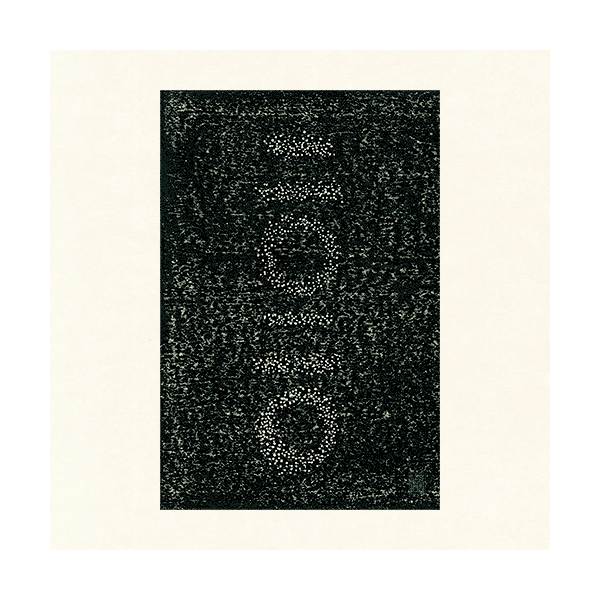絵本『森の家』 / picture book



ある朝のこと、木こりはいつものように仕事に出ようと思って、おかみさんに言いました。
「わしの昼飯は、一番上の娘に森まで持たせてよこしてくれ。そうしないと仕事がすまないからな。」
それからまた、こうつけ加えました。
「あれが道に迷わぬように、キビを一袋持って行って、途中にまいておこう。」

ところが野スズメ、森スズメ、ヒバリ、ウソ、ツグミ、マヒワ、などいろいろな鳥が、とっくの昔にキビをついばんでしまって、娘には道がちっとも分かりませんでした。
そこで娘は、運を天にまかせて、やたらに歩き続けましたが、とうとう日が沈んで夜になりました。

娘はだんだん恐ろしくなりました。
そのとき、娘は遠くのほうに、木のまがくれにともしびが一つ、チラチラするのを見つけました。
「あそこへ行ったらきっと人が住んでいて、一晩泊めてくれるだろう。」
娘はこう考えて、その明かりを目当てに歩いて行きました。

戸をたたきますと、家の中からしわがれた声で、
「おはいり。」
と言いました。
戸を開けてみますと、年とって氷のような白髪の人がテーブルに向かい、座っていました。
その白いひげは、テーブルの上からほとんど床の上までたれています。
暖炉のそばには、メンドリとオンドリとぶちの雌牛と、この三匹の動物がいました。
娘が老人に自分の身の上を話して、一晩泊めてくださいと頼みますと、その人が言いました。
「きれいなメンドリ、
きれいなオンドリ、
きれいなぶちの牛、
おまえたちはどう思う?」
「ドゥクス!」
動物たちはこう答えました。これはきっと、
「ぼくたちはそれでもいい。」
という意味に違いありませんでした。
「うちには何でもたくさんあるから、炉端へ行って、わしらの晩ごはんをたいておくれ。」

そこで、おいしいごちそうを作りました。
しかし娘は、動物たちのことなど少しも考えませんでした。
娘は山もりのお皿をテーブルに出し、老人のわきに座って食べ、ひもじいおなかをいっぱいにしました。
食べ飽きてしまうと娘は言いました。
「私、もう疲れてしまったわ。私の寝床はどこかしら。」
すると動物たちが答えました。
「おまえはおじいさんと一緒に食べて、
おまえはおじいさんと一緒に飲んで、
わしらのことなど考えぬ。
今夜の寝床に気をつけな。」
すると老人が言いました。
「さあ、その階段をお上がり。ベッドを二つ置いてある部屋がある。そのふとんをふるってふっくらとさせ、それから白いリンネルのかけぶとんをかけといておくれ。わしも行って休むから。」

ところがしばらくすると、おじいさんがやって来て、あかりで娘の顔を照らし、頭をふりました。
そして娘の寝込んでいるのを見ますと、おとし戸を開いて娘を穴ぐらにおろしてしまいました。

「私が悪いんじゃありませんよ。あの子は昼ご飯を持って出て行ったんです、きっと道に迷ったに違いありません。明日になれば帰って来ますよ。」
おかみさんはこう言いました。
木こりはあくる日、夜もあけないうちから起きだして森に行こうと思い、こんどは二ばん目の娘に、弁当を持って来るように言いつけました。
「アズキを一袋持って行こう。キビなんかよりつぶが大きいから、娘にもよく分かって、道を間違えるようなこともあるまい」

ところが、アズキはかげも形もありません。まえの日と同じように、森の小鳥たちがついばんでしまって、ひとつぶも残ってはいなかったのです。
娘はとうとう夜になるまで森をさまよい歩き、日の暮れた頃、例の老人の家にたどり着きました。
そして中に呼び込まれたので、食べ物と宿を頼みました。
白いひげの老人は、また動物たちにたずねました。
「きれいなメンドリ、
きれいなオンドリ、
きれいなぶちの牛、
おまえたちはどう思う?」
動物たちは今度もまた、
「ドゥクス!」
と答えました。

娘はおいしい料理を作って、おじいさんと飲んだり食べたりしました。
しかし動物たちのことは、少しも考えてやりませんでした。
娘が自分の寝床を聞きますと、動物たちは言いました。
「おまえはおじいさんと一緒に食べて、
おまえはおじいさんと一緒に飲んで、
わしらのことは考えない。
今夜の寝床に気をつけな。」
娘が寝入ってしまうとおじいさんがやってきて、その顔尾をしげしげながめて頭をふり、
穴ぐらの中に落としてしまいました。

「今日は末の娘に弁当を持たせてよこしてくれ。あれはいつも気だてのいい、すなおな子だから、道草なども食わないで、おてんば者の姉たちみたいに、ほっつきまわりもしないだろう。」
おかみさんはしかし、こんどは承知しないで言いました。
「また私たちの、一番かわいい子供まで、なくしてしまうのかい。」
「心配無用さ、あの子ならりこうで、ものわかりはよし、迷ったりなんかするものか。
それに今度は、エンドウ豆を持って行ってまくつもりだから、アズキなんぞよりずっと大きいし、あの子の道しるべには大丈夫だ。」
木こりはこう答えました。

「あたしだけが満足して、動物にはなにもやらないって事があるかしら。」
娘は外へ出て、大ムギを持って来てメンドリとオンドリにまいてやり、牝牛にはにおいのよいほし草を両腕いっぱい持って来てやりました。
「さあ、みんなおあがりなさい。のどがかわいているなら、くみたての水もあげるわ。」
それから桶いっぱい水をくんできました。メンドリとオンドリとは桶のふちに飛び上がって、水にくちばしを入れては、天井のほうを向いて、小鳥のようにして水を飲みました。牝牛は牝牛でぐいぐいと大口に飲みました。
それから娘はおじいさんと並んでテーブルにつき、おじいさんの残りのものを食べました。
しばらくしますと、メンドリもオンドリも、そろそろ小さいあたまを羽の中にうずめ、牝牛は目をしょぼしょぼさせました。そこで娘は言いました。
「あたしたち、もうお休みにしたらどうでしょう。
きれいなメンドリ、
きれいなオンドリ、
きれいなぶちの牛、
おまえたちはどう思う?」
すると動物たちは答えました。
「ドゥクス!
おまえはわしらと一緒に食べて、
おまえはわしらと一緒に飲んで、
わしらみんなによくしてくれた。
ごきげんよろしゅうおやすみなされ。」

娘は心配でなりませんでした。そして、かわいそうにお父さんがさぞひもじかろう、家へ帰れなかったらお母さんがどれほど悲しむかしらなどと、たえずそのことばかり気にかけていました。
とうとう日がとっぷりと暮れますと、娘は小さな明かりをみとめました。
あの森の家のところへきたのでした。
娘は丁寧に、一晩、宿をかしてはいただけないでしょうか、と頼みました。
するとあのしろひげの老人が、また動物たちに訪ねました。
「きれいなメンドリ、
きれいなオンドリ、
きれいなぶちの牛、
おまえたちはどう思う?」
すると動物たちは言いました。
「ドゥクス!」
そこで娘は、動物たちの寝ていた暖炉のところへ行って、メンドリとオンドリのすべすべした毛なみをなでてやり、またぶちの牝牛の二本の角の間をこすってやりました。

それがすむとおじいさんがやって来て、ひとつの寝床に入りました。
娘は別の寝床に入り、お祈りをして眠りました。
娘は夜中まで静かに眠りましたが、夜中になると家の中がひどく騒がしくなったので、目を覚ましてしまいました。そのうち、すみずみまで、ギシギシ、ガタガタいいはじめ、戸がパッとあいて壁にぶつかったりしました。はりがつぎめからひきさけでもするように鳴りとどろき、階段が落ちたかと思われるような音がし、とうとうさいごに、屋根全体の静けさにかえると、娘には何のこともなく、そのままもう一度寝入ってしまいました。

娘が寝ていたのはある大広間で、まわり一面何から何まで、おおさまの御殿のように立派に輝きわたり、壁には緑のきぬ地に、金泥の花がすくすくと伸び、ベッドは象牙、かけてあるふとんは赤のビロード、そばのいすの上には、真珠をちりばめた上靴が置いてあります。
これは夢であろうと娘は思いました。
ところが、立派な身なりをした三人の召使いがやって来て、ご用はございませんかとたずねました。
「いいからいってください。」娘は答えました。
「わたしがすぐに起きておじいさんのスープを煮ましょう。それからきれいなメンドリとオンドリ、それにきれいなぶちの牝牛にも、えさをやりますわ。」

ところが中に寝ていたのは、おじいさんではありません。見知らぬどこかの男の人です。
よく見ますと、若い美しい人でした。目を覚ましたその人は、起き上がって言いました。
「わたしは王子の身の上なのだ。ところが悪い魔法使いのために魔法をかけられ、氷のような白髪の老人となって森で暮らしていた。メンドリ、オンドリ、ぶちの牝牛、こういう姿をした三人の召使いのほかには、だれひとりお供を許されなかった。そして、心底から気だてがよく、人間はおろか、鳥けものにまでやさしくしてくれる乙女の来るまでは、このまじないは解けないこととなっていた。
さて、その乙女というのは、そなたであった。ゆうべの真夜中に、わたしたちはそなたによって救われた。そして森の古家は、再びわたしたちの宮殿になったのだ。」
みんなが起き上がりますと、王子は三人の召使いに、馬車に乗って、娘の父と母とを婚礼の祝いに連れて来るよういいつけました。
そのとき娘がたずねました。
「ところで私の二人の姉はどうしたのでしょう。」
「あの者どもは、わたしが穴ぐらに閉じ込めておいた。明日は森に引き出されて、性根がなおり、あわれな鳥けものにひもじい思いをさせぬようになるまで、炭やきのところで召使いとなっていなければならない。」
そうして二人の姉は間もなく家に戻り、三番目の娘と王子は末永く幸せに暮らしました。


水性木版画, デジタル編集
Waterbase Woodblock Print, Digital editing
25.7×36.4cm 2015